子どもには本を好きになってほしい。
そんな思いから、我が家で実際にやってきた工夫をまとめました。
1. 読み聞かせを続ける
小さいころから読み聞かせをしました。
毎日は無理でも「できる日だけでも続ける」ことを大切にしました。
長い物語は数日に分けて読み、いちばん長かった本は「泥棒の神様」で2週間以上かかりました。
正直「面倒だな」と思うこともありましたが、子どもによって反応が違うのも面白かったです。
- 上の子 → 読んでもらうのを待つタイプ
- 下の子 → 先が気になって勝手に読むタイプで、自然と本好きになりました
2. 毎月届く本のサービスを利用
祖母が「孫に毎月一冊本を贈るサービス」を使ってくれていて、毎月2冊の本が届きました。
定番の絵本から初めて出会う本まで、幅広いジャンルに触れられたのが良かったです。
3. 本屋や図書館で「1冊は選ぶ」ルール
本屋や古本屋、図書館に行ったら、子どもが好きな本を1冊選ぶルールにしました。
基本は漫画以外ですが、「たまには漫画でもOK」にして、選ぶ楽しさを優先。
妖怪や毒を持った動物の本など「えっ?」と思うようなものでも、選んだものはOKにしました。
4. 子どものおすすめ本は親も読む
小学校の学級文庫や図書館で借りた本を、子どもが「面白かった」と言ったら、できるだけ自分も読むようにしました。
同じ本を共有すると、会話も増えて「読書って楽しいね」という空気になったと思います。
5. 好きなジャンルを尊重
- 下の子 → 小学校中学年で伝記にはまり、その後は推理小説・ライトノベル・小説と幅広く読んで、本好きに成長
- 上の子 → あまり読まなかったが、気に入ったシリーズは読むようになった
「漫画でも活字は活字」と考えて、あまり細かく制限しなかったのが良かったと思います。
本は捨てずにとっておく
お気に入りの本は、かさばっても大事に残しています。
自分が親になってから「あの本を子どもに読ませたい」と思って探し直した経験があるからです。廃版の本を中古で探してまで手に入れたこともありました。
懐かしい絵や物語に再会すると、自分自身がわくわくして満たされます。
まとめ
我が家では「読み聞かせ」「選ぶ楽しさ」「親も一緒に読む」という工夫を通して、本との距離を近づけました。
上の子はそこまで本好きではないけれど、下の子は自然と本好きになり、国語が得意です。
子どもの同級生で東大や医学部に入った子も本好きが多く、うちの下の子も現役で医学部に進学しました。
読書は楽しいだけでなく、学力や思考力にアップにつながるのは間違いないのかなと思います。
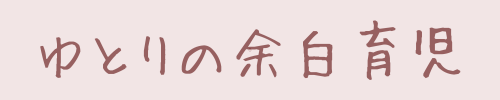



コメント