成績が下がったとき、声かけは難しい
子供の成績が下がったときの声かけって、本当に難しいと思います。
こっちが励ますつもりでも、逆に怒らせたり、落ち込ませてしまうことも。怒るのも良くないだろうし…。
親もわからない難しさに気づいた瞬間
私自身も進学校から大学受験を経験しました。
でも、子供が高校に入って「勉強が分からない」と言ったとき、試しに数Ⅰの教科書を見てみたら――全く分からなかったんです。
「まさか」と思って解答を見てもさっぱり。解説を読んでも「???」。
あぁ、子供はこんなに難しいことをやっているのか、と。
しかも高校のときに得意だったはずの数Ⅰすら理解できなくなっている自分に衝撃を受けました。
でも同時に、「今の仕事で全然使ってないし、これが分からなくても社会では困らないな」とも思ったのです。
その経験があったからか、高校生以降は子供に勉強のことで強く言ったことはほとんどありません。
親が解けない問題をやっているのに、「勉強しろ」と言える資格はないなと感じたからです。
子供の成績の波と「物理」の壁
子供の成績は、進学校ということもあり、少し下がってもすぐ上がるわけではありません。
大きく上下するのではなく、波のように上がったり下がったりを繰り返していました。
理系が得意でしたが、物理で二度ほど大きく点を落としたことがあります。
1回目にガクッと下がったときは、「物理はわかる?」と聞いたら、
「点は取れなかったけど分かる」との返事。
でも2回目にまた大きく下がったときは、平均も大きく割ってしまい、さすがにまずいと思いました。
ちょうど面談があり、担任の先生(物理担当)に相談したところ、
「物理は単元ごとに内容がガラッと変わるので、得意分野は理解できても、苦手分野になると全然ついていけないことはよくある」
とのことでした。私は物理を選択していなかったので、そんなことも知りませんでした。
実際にかけた言葉と対応
そこで子供にかけた言葉は、
「じゃあ、お金出すから問題集を買いに行こうか」でした。
普段はケチで渋るタイプでしたが、そのときは外食ついでにショッピングモールに寄り、本屋へ。
「この分野はこの本がいいけど、別の分野はこっちの本の方がいい」なんてこともよくあるので、
「3冊くらい買っていいよ」と言ったのですが、子供が選んだのは迷った末に薄い問題集1冊。
問題集を選んだその後の変化
それがよかったのか、次の物理は平均点を超えてきました。
成績が少し回復して、私もホッとしたのを覚えています。
まとめ:親にできるのは環境づくりと支え
子供の成績が下がったとき、親としてできることは限られています。
無理に勉強を教えるよりも、環境を整えてあげることや、必要なときに支えることの方が大事だと感じました。
点数が上がるか下がるかに一喜一憂するよりも、長い目で見て「自分で学ぶ力」を育てること。
それが親にできる一番のサポートなのかなと思います。
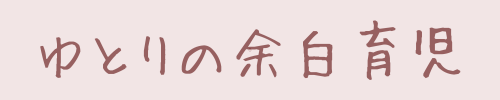
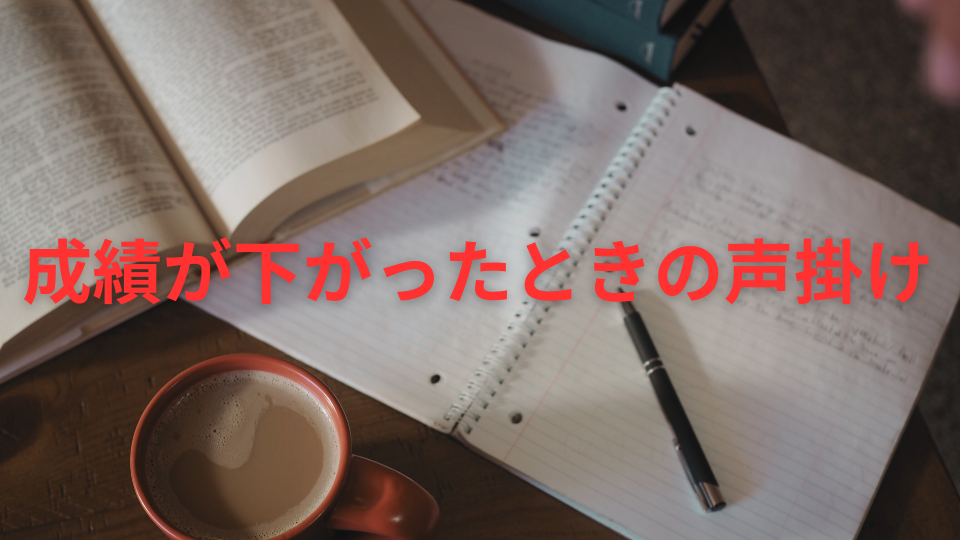
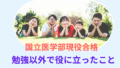

コメント