「できる子はリビングで勉強する」「勉強机はいらない、食卓で十分」等の説、一度は目にしたことはないでしょうか。
実は、我が家もこの「リビング学習」を実践し、現役で国立医学部に合格しました。
この記事では、現役合格につながった、我が家のリビング学習の「環境づくり」と「親の見守りスタンス」について、詳しくご紹介します。
💡 第1章:リビング学習を可能にした環境づくり
子どもが小学校に上がるタイミングで家を建てた際、私たちはリビング学習を最優先しました。
✅ LDKに「学習机を置ける広さ」を確保
我が家は一階がLDK(リビング・ダイニング・キッチン)、二階に主寝室と子供部屋という間取りです。
設計で最も意識したのは、LDKに子どもの学習机を常設しても、家族の生活空間を圧迫しない広さを確保することでした。
リビングの雰囲気を壊さないよう、カリモクなどで見つけた「学習机感の少ない」シンプルなデザインの机を選びました。この専用の机を、リビングの片隅に設置しました。
少しサイズが小さくなるかもしれませんが、無印良品などもよいと思います。
✅ 学習用品はすべて1階に
共働き世帯としての利便性を考慮し、ランドセルや学習用品はすべて1階(リビング周り)に置くことを徹底しました。
リビングにランドセルがあるのは生活感丸出しですが、小学校低学年の時は、親のチェックが必要な宿題が多く、すぐにランドセルがあるのは非常に便利でした。2階の子ども部屋は、衣類や備品の置き場として利用し、学習環境とは完全に切り離していました。
🏠 第2章:食卓でなく、専用机をリビングに置いた理由
我が家が食卓で勉強させるのではなく、リビングに学習専用の机を置くことにこだわった最大の理由は、学習の中断と再開のハードルを下げるためです。
✅ 途中中断もスムーズに
例えば、宿題の途中で夕食の時間になったとします。食卓で勉強していると、途中のプリントや参考書をすべて片付けてからでないと、夕食の準備や食事ができません。
しかし、リビングに専用の机があれば、子どもが「ご飯ができたから、いったん手を止めて箸を並べて」と手伝いに向かう際、宿題を机に広げたままの状態にしておけます。
✅ 再開のハードルを下げる工夫
小さな頃は、いちいち広げたものを片付けてしまうと、子どもの「また勉強に戻る」という意欲を削いでしまうと考えました。自分の机に学習途中の状態を残せることで、食後すぐにスムーズに続きを再開できました。
もちろん、子どもが「あと少しでキリがいいから」という時は優先させましたが、そうでない場合は中断を恐れず生活リズムを優先させる運用でした。この「再開のしやすさ」が、勉強を習慣化させる上で非常に大切だと考えています。
🗣️ 第3章:合格に繋がった「見守りスタンス」の徹底
小学校低学年までを想定していたリビングへの机の設置は、結局、小学校高学年まで続けました。リビング学習の成功には、親の関わり方が最も重要でした。
✅ 「勉強しなさい」は禁句
我が家では、「勉強しなさい」という直接的な命令は言いませんでした。子どもが自分でやるべきことを認識し、自ら学習に向かう姿勢を尊重したかったからです。
代わりに、以下のような「確認」や「見守り」のスタンスで声をかけました。
- 「宿題できてる?」
- 「大丈夫?間に合う?」
親は家事や自分の用事をしながら、子どもに背を向けるなどして干渉しすぎないように意識しました。「監視」ではなく「見守り」の距離感を保ち、「いつでも頼れる安心感」だけを与えました。
✅ 快適さと自律性の法則
中学に入り、リビングから学習机を撤去した後、興味深い傾向が見られました。
- 勉強が得意な子:床暖房など、「環境の快適さ」を求め1階で勉強することが増える。
- 勉強に苦手意識がある子:「親の目」が届かない2階の自室に行くことが増える。
この経験から、「集中して勉強するには環境の快適さが優先され、好きなことをする(サボる)には親の目が届かない場所が快適」という結論に至りました。
🌟 総括:環境が育んだ難関突破力
我が家のリビング学習は、「再開しやすい専用机の環境」と「干渉しすぎない見守りスタンス」の徹底により、子どもが自律的に学習を進める力を育みました。
この環境で育まれた「自分で学習を管理する力」こそが、中学以降の難関な学習、そして最終的な国立医学部現役合格という結果に繋がったと考えています。
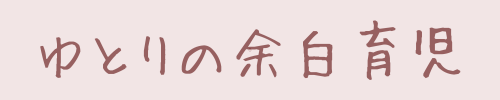
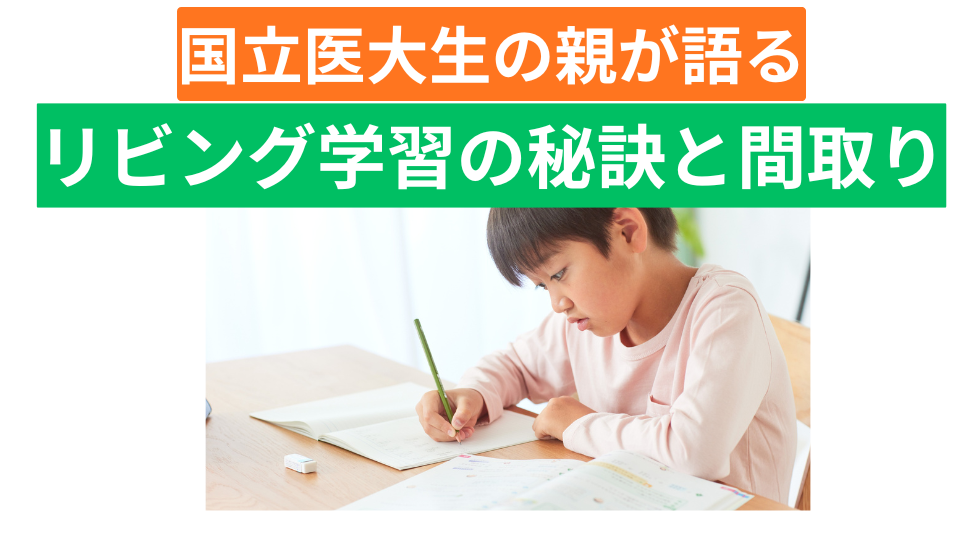
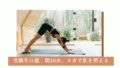
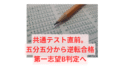
コメント