子供が小さい頃、どんなおもちゃを与えるか悩む親は多いと思います。
うちの子は国立大学の医学部に通っていますが、小さい頃の「遊び」が今の力につながっていたのかもしれません。
もちろん、おもちゃは、勉強ができる子に育てようと思って買ったわけではありません。
小さい頃はただ、夢中で遊んでほしいという気持ちだけでした。
子供が大人になった今、振り返ってよかったと思うおもちゃを紹介します。
赤ちゃん期:積み木で手を動かしながら考える
最初に与えたのは積み木。
質の良い自然派の積み木もありましたし、いとこからのおさがりもありました。
高く積んだり、崩したり、形を組み合わせて遊ぶうちに、集中力や空間認識能力が自然と育ったように思います。
幼児期:トミカ・プラレールで仕組みに興味を持つ
少し大きくなると、トミカやプラレールに夢中になりました。
ただお手本通りにつなぐだけでなく、自分で新しいルートを考えて線路をつなげたり、立体的なコースを作ってみたし。
どうしたらうまく走るか、何度も試しながら遊ぶうちに、自然と試行錯誤する力がついていったように感じます。
小学校前後:くもんのクミクミスロープやレゴで論理的思考を育てる
ボールが転がるコースを自分で組み立てて、思った通りに動くかを試す。
うまくいかないと何度も組み直していました。
この「考えて→試して→直す」流れが、のちに理科や数学の理解にもつながったようです。
同じ組み立てる系では、レゴやプラモデルも夢中になって遊んでいました。
小さい頃は誤飲防止のための大きなレゴ、大きくなったら小さいレゴへ移行。
おさがりをたくさん頂いたので、少しだけ必要なパーツを買い足しました。
戦隊ヒーローごっこ:物語を作る力(想像力と表現力)を伸ばす
もちろん、戦隊ヒーローにハマった時期もありました。
その頃はベルトや武器のおもちゃも買ってやりました。
一見ただの“ごっこ遊び”ですが、ストーリーを作ったり、役になりきったりすることで、想像力や表現力が育っていたと思います。
おうちごっこ:本物でリアルに
おままごとではたくさん野菜や道具があった方が楽しいので、100均のおもちゃも使いましたが、
私が使わなくなったフライパンやお玉を渡すと大喜び!
色々なアイテムを組み合わせることで、遊びに現実感が増し、想像力がさらに広がりました。
その延長の「おうちごっこ」もよくしていました。
お母さん役やお店屋さん役を決めて、セリフを考えながら遊ぶうちに、
言葉の使い方や相手の気持ちを想像する力が育ったように思います。
小さな会話の積み重ねが、コミュニケーション力の土台になったのかもしれません。
ピタゴラスイッチごっこ:試行錯誤の面白さに夢中
テレビのピタゴラスイッチを見て、自分でまねして装置を作っていました。
レゴやくみくみスロープ、プラレールなど手持ちのおもちゃやビー玉や段ボール、積み木を組み合わせて「どうしたら最後まで転がるか」を試す姿は、まるで小さな研究者。
立体的なつながりを考えるこの遊びは、空間のイメージ力を育て、図形や構造を理解する力にも役立ったと思います。
You Tuberのようにスマホで撮影するところは最近の子だなと実感しました。
まとめ
おもちゃ選びで特別な意識はありませんでしたが、共通していたのは想像力を使う遊びだったこと。
特別に高価な知育玩具を揃えなくても、子供が夢中になれる環境を整えてやること大事だったと思います。
積み木、トミカ、プラレール、くみくみスロープ、レゴ、おうちごっこ、戦闘ごっこ、
どれも自由で正解のない遊びです。
自分で考えて、失敗して、もう一度やり直す。
その繰り返しこそが、後の学びにつながる一番の力になったのかもしれません。
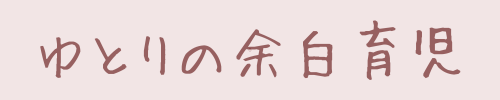

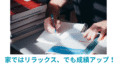
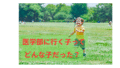
コメント